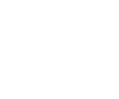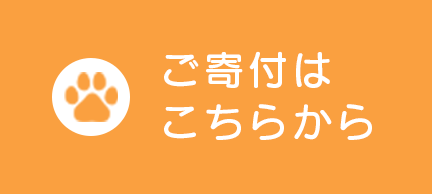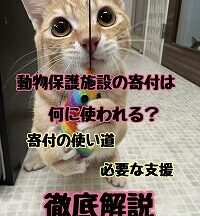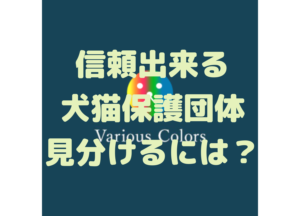イメージしてみましょう!
保健所に収容された一匹の猫がいます。小さなケージの中で、じっと外を見つめるその瞳には、不安と寂しさが漂っています。
ここに来る前は誰かに愛されていたのかもしれません。それともずっと野良猫として生きてきたのかもしれません。
実際どうだったかは分かりません。ただ一つ確かなのは、皆様に譲渡される機会がなければ、この猫の命は終わってしまうというのが現実です。

日本では、毎年多くの猫が保健所に収容され、そのうちの一部が新しい飼い主に巡り会えずに殺処分されています。
しかし、そんな猫たちを救う方法があるのをご存じでしょうか? 保健所や動物愛護センターから猫を迎え入れることで、たった一匹でも「助かる命」を増やすことができるのです。
本記事では、保健所の猫を迎える意義や準備、手続き、注意点を詳しく解説し、あなたと猫が幸せに暮らすための第一歩をお手伝いします。
【目次】
1. はじめに
・保健所の猫たちを迎える意義
・殺処分の現状を知る
2. 保健所の猫たちの現状とは
・保健所での猫の環境
3. 猫を迎えるための準備
・必要な物品(キャリーバッグ、食事、トイレなど)
・家族との話し合いと迎える心構え
4. 保健所から猫を引き取る流れ
・保健所や動物愛護センターでの譲渡手続き
・必要な書類や費用
5. 譲渡を受ける際の注意点
・健康管理(ワクチン接種や健康診断)
・新しい環境に慣れるための工夫
・終生飼育の覚悟
6. 保健所以外の選択肢
・ボランティア団体や譲渡会の活用
・インターネットでの情報収集
7. まとめ
はじめに
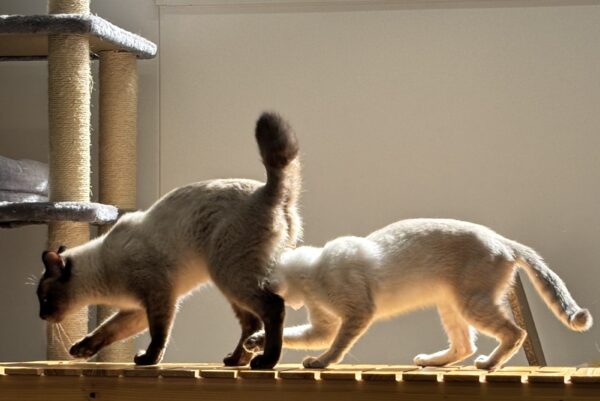
保健所の猫たちを引き取る意義
近ごろは、ペットショップやブリーダーからだけでなく、保健所や動物愛護センター、猫の保護施設から猫を引き取る人も増えています。
そこには、さまざまな事情で飼い主を失った猫や、生まれたばかりで行き場のない子猫など、命の危機にある猫たちが多くいます。
こうした現状を知り、保健所の猫を引き取ることには大きな意味があるのです。
1.命を救う選択
保健所では、収容された動物の数が多すぎる場合や引き取り手が現れない場合、殺処分が行われることがあります。
日本では、年間数万匹以上の猫が殺処分されているという現実があります。この現状を変えるためには、私たち一人ひとりが保健所の猫を迎え入れ、命を繋ぐことが重要です。一匹でも多くの猫に新しい家庭を提供することは、殺処分の数を減らす具体的な行動です。
2.ペットショップ依存を減らす
ペットショップでは、販売のために無理な繁殖を繰り返している場合があります。
その結果、親猫が劣悪な環境で飼育される問題が発生しています。保健所の猫を迎えることで、こうした不適切な繁殖ビジネスに依存しない選択をすることができます。
3.多様な猫との出会い
保健所には、雑種や純血種、年齢や性格が異なる多様な猫たちが収容されています。
ペットショップでは出会えないような猫に出会えるチャンスがあり、自分に合った性格の猫や特別なストーリーを持つ猫を家族に迎えられる可能性があります。
4.命の重みを考えるきっかけ
保健所から猫を迎える過程は、動物の命の大切さを改めて考える機会となります。
迎えた後も「この猫の命を救えた」という強い責任感や充実感を得ることができ、飼い主としての意識も高まります。
5.地域社会への貢献
保健所や動物愛護センターの活動は、地域社会で問題となっている動物の保護や適正飼育に直結しています。
保健所から猫を迎えることは、これらの活動を支援し、地域全体の動物福祉向上に貢献する行動です。
猫を迎える際、どのような方法を選ぶかは個人の自由ですが、保健所の猫を選ぶことで得られる満足感や命を救ったという実感は特別なものです。
この行動は猫だけでなく、自分自身や地域社会にも良い影響をもたらします。保健所の猫たちを迎える選択は、私たちの小さな一歩が大きな命の救済につながることを示す、非常に価値ある行動です。
殺処分の現状を知る
日本では、保健所や動物愛護センターに収容された猫の中には、飼い主が見つからないまま殺処分されてしまうケースが少なくありません。
猫たちがこのような悲しい運命を辿る背景を知ることは、私たちが何をすべきかを考える第一歩です。この問題の現状と原因、解決に向けた取り組みについて見ていきましょう。
1.日本の殺処分数の実態
過去数十年にわたる動物愛護活動の進展により、殺処分数は徐々に減少していますが、それでも多くの猫が命を落としています。
環境省のデータによれば、2020年度には全国で約17,000匹の猫が殺処分されました。この数はピーク時に比べて大幅に減少しているものの、まだ課題が残っています。
2.猫が保健所に収容される理由
保健所に収容される猫にはさまざまな事情があります。
・飼い主の持ち込み(引っ越しや経済的な理由)
・迷子になった猫
・野良猫やその子猫の捕獲
・去勢・避妊をしなかった結果の「計画外の繁殖」
こうした背景から、多くの猫が行き場を失っています。
3.殺処分が行われる理由
保健所にはスペースや人員、予算の限界があります。
一定期間に新しい飼い主が見つからない場合や、病気・高齢・性格的に譲渡が難しい猫は、殺処分の対象になってしまいます。
4.殺処分の方法とその課題
日本の保健所では、炭酸ガスを使用した窒息死が主な殺処分の方法として用いられています。
この方法は比較的苦痛が少ないとされていますが、それでも完全に痛みや恐怖をゼロにすることは難しく、動物愛護の観点から議論の余地があります。
そもそも「命を奪う方法があること」自体が、多くの人にとって衝撃的な現実です。
5.殺処分を減らすために私たちができること
私たちにできる行動は小さくても大切です。
・保健所から猫を引き取ること
・飼い猫や地域猫への去勢・避妊手術の徹底
・動物愛護団体の支援やボランティア参加
これらを積み重ねることで、一匹でも多くの命を救えます。
6.行政や地域社会の役割
行政も譲渡促進プログラムや地域猫活動の支援などを進めています。地域社会全体で取り組むことが、殺処分を減らす大きな力になります。


殺処分の現状は非常に深刻な問題ですが、これを知ることで私たちは何ができるのかを考え、行動に移すきっかけとなります。
一匹でも多くの猫が新しい家庭を見つけ、幸せな生活を送れるよう、命の重さを理解し、あなたができることから始めましょう。それがとても大切なことです。
保健所の猫たちの現状とは

保健所に収容された猫たちは、どのような環境で過ごしているのでしょうか?
保健所の設備や管理体制には地域による違いがありますが、基本的に猫たちは限られたスペースの中で一定期間を過ごし、譲渡先が見つからない場合は殺処分の対象となってしまうケースも少なくありません。
ここでは、保健所での猫の生活環境や課題、改善への取り組みについて詳しく解説します。
1.保健所に収容される猫の種類
保健所に収容される猫には、さまざまな背景を持つ猫がいます。
・飼い主が持ち込んだ猫
飼えなくなったという理由で飼い主自ら持ち込むケースがあります。中には高齢や病気を理由に持ち込まれる猫もおり、引き取ることが難しくなることもあります。
・野良猫や迷い猫
捕獲された野良猫や、迷子になって飼い主が見つからない猫も収容されます。特に子猫の場合、母猫とはぐれてしまい衰弱しているケースも多くあります。
・繁殖制限されていない猫の子猫
飼い主の管理不足によって生まれた子猫が、引き取り手が見つからずに保健所へ持ち込まれることもあります。
2.保健所での猫の収容環境
保健所に収容される猫の環境は、各施設の設備や人員によって異なりますが、一般的には以下のような特徴があります。
① 限られたスペース
多くの保健所は動物専用の大きな施設ではなく、限られた場所で猫を管理しています。
そのため、個別のケージに入れられることが多く、猫同士が触れ合う機会はほとんどありません。
② ストレスの多い環境
犬や他の動物も一緒に収容されているため、鳴き声や匂いにより猫が強いストレスを感じることがあります。
慣れない環境に不安を覚え、警戒心が強まる猫も少なくありません。
③ 衛生管理の難しさ
清潔な環境を保つ努力はされていますが、人手が足りないと十分なケアができないこともあります。
また、狭い場所に多くの猫が集まると、感染症が広がるリスクも高まります。
④ 譲渡対象の選別
健康で落ち着いた性格の猫は譲渡の対象となり、新しい飼い主が見つかるまで保護されます。
一方で、病気や高齢の猫、極端に警戒心が強い猫は、譲渡が難しく、残念ながら殺処分の対象になることもあります。
3.保健所の取り組みと改善策
① 譲渡を前提とした保護活動
以前は収容された猫がすぐに殺処分されるケースも多くありました。
しかし今では、一定期間は譲渡活動を行い、できるだけ新しい飼い主を探す努力がされています。
その一環として、譲渡会の開催やSNSを活用した情報発信も広がっています。
② 動物愛護センターとの連携
一部の地域には、保健所とは別に動物愛護センターが設けられています。
ここでは、より良い環境で猫を保護し、新しい飼い主と出会えるように活動が行われています。
③ 地域ボランティアとの協力
地域の動物愛護団体やボランティアと連携し、一時的に猫を保護したり、里親探しをサポートしたりする活動も増えています。
④ 地域猫活動(TNR活動)の推進
野良猫を捕獲し、不妊・去勢手術をして元の場所に戻す「TNR活動」も広がっています。
この取り組みによって野良猫の数を減らし、保健所に持ち込まれる猫を少なくすることで、殺処分を防ぐことにつながっています。

保健所の猫たちは、限られた環境の中で新しい飼い主を待っています。
しかし、スペースや人手の不足、ストレスの多い環境など、多くの課題が存在します。行政やボランティア団体の努力によって改善が進んでいるものの、最も重要なのは一人ひとりの意識と行動です。
保健所の猫たちの現状を理解し、譲渡や支援活動に目を向けることで、救われる命を増やすことができます。
猫を迎えるための準備
保健所から猫を引き取る前に、必要な準備し、家族としっかり話し合うことが大切です。
必要な物品(キャリーバッグ、食事、トイレなど)

猫が安心して新しい生活を始められるように、次の道具をそろえるのがおすすめです。
① キャリーバッグ
譲渡のときや動物病院に行くときに必ず必要です。丈夫で通気性の良いタイプを選びましょう。
② 食事(キャットフード)
猫の年齢や健康に合ったフードを用意します。最初は、保健所で与えられていたものに近いフードを選ぶと安心です。
③ トイレと猫砂
猫専用のトイレと猫砂を準備します。猫によって好みが違うので、様子を見ながら合うものを探しましょう。
④ ベッドや隠れ場所
猫は安心できる場所を必要とします。専用のベッドや、狭くて落ち着けるスペースを作ってあげましょう。
⑤ 爪とぎ
家具や壁を守るために、猫専用の爪とぎを用意します。
⑥ おもちゃ
運動不足やストレスを防ぐために、おもちゃも大切です。遊びを通じて猫との信頼関係も深まります。
家族との話し合いと迎える心構え

猫を引き取る前に、ご家族全員でしっかり話し合いましょう。
①アレルギーの確認
家族に猫アレルギーの人がいないか事前に確認しましょう。
②飼育のルールを決める
猫をどの部屋で飼うか、しつけの方針、家族の役割分担などを決めておくとスムーズです。
③長期的な責任を持つ覚悟
猫の寿命は15~20年ほど。最後まで責任を持って飼育できるかを考えましょう。
保健所から猫を引き取る流れ

保健所や動物愛護センターでの譲渡手続き
保健所で猫を迎えるための流れは、以下のようになります。
①情報収集
地域の保健所や動物愛護センターのホームページを確認し、譲渡可能な猫を探します。
②見学・相談
引き取り希望の猫が決まったら、施設を訪問し、職員と相談します。
③譲渡審査
施設によっては、飼育環境や飼い主の責任感を確認するための審査があります。
④トライアル期間(ある場合)
一部の施設では、試しに数日~数週間猫を飼ってみる「トライアル制度」を設けています。
必要な書類や費用
保健所での猫の譲渡には、以下の書類や費用が必要になる場合がありま
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・飼育環境を証明する写真
・譲渡費用(ワクチン接種費用など、5,000円~20,000円程度の場合も)
保健所から猫を引き取る際の注意点

健康管理(ワクチン接種や健康診断)
保健所の猫は、健康状態が不明な場合が多いため、迎え入れたらすぐに動物病院で健康診断を受けましょう。
ワクチン接種:感染症予防のために必須です。
寄生虫駆除:ノミやダニ、回虫などの駆除を行うことが推奨されます。
避妊・去勢手術:猫の健康維持や望まない繁殖を防ぐため、適切な時期に手術を検討しましょう。
新しい環境に慣れるための工夫
猫は環境の変化に敏感な動物です。
最初は静かな環境を作る:初めの数日は無理に触らず、落ち着けるスペースを作ってあげましょう。
少しずつ家に慣れさせる:いきなり家中を自由にさせず、まずは1つの部屋から慣れさせると安心します。
終生飼育の覚悟
猫は長生きする動物です。
一度迎えたら、最後まで責任を持って世話をすることが大切です。
猫と暮らすご家族が5名いるのであれば、かならず5名全員の意思確認が必要でしょう。しっかりご家族内で話し合うべきです。

保健所以外の選択肢
■ボランティア団体や譲渡会の活用
保健所以外にも、ボランティア団体が保護猫の譲渡活動を行っています。譲渡会では、事前に猫の性格を知ることができるメリットがあります。
■インターネットでの情報収集
里親募集サイトやSNSを利用して、保護猫の譲渡情報を探すことも可能です。ただし、信頼できる団体から迎えることが重要です。
まとめ
保健所から猫を迎えることは、命を救う選択です。しかし、それには事前準備や心構えが必要です。猫を家族として迎えることをしっかり考え、最後まで愛情を持って育てられるようにしましょう。
新しい猫との生活は、大変なこともありますが、それ以上に幸せや喜びをもたらしてくれます。一匹でも多くの猫が、温かい家庭で幸せに暮らせるように、私たちができることを考えていきましょう。
ヴァリアスカラーズでは、殺処分ゼロを目指して里親募集や寄付の受け付けも実施しております。
少しだけでも何か出来たらと思っていただけましたら、ご協力をお願いいたします。
皆さまからのご支援が私たちの、そしてなにより犬猫の生きる力になります!
1頭でも多くの命を救うために、ぜひご支援・ご協力をお願いいたします。
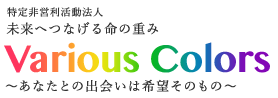


■保護犬猫紹介ページ こちらをクリック ⇒ [犬猫里親募集]
■団体インスタグラム こちらをクリック ⇒ [インスタグラム]