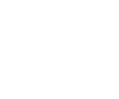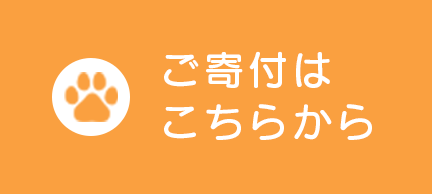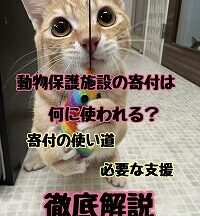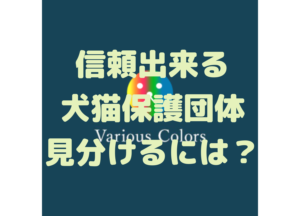「殺処分される犬や猫を引き取りたい」と思ったとき、どうしたらよいのでしょうか?
テレビやSNSで現実を知り、「自分にできることはないか」と考える方は少なくありません。
実際に引き取るには、主に以下の方法があります。
・自治体の保健所や動物愛護センターに申し込む
・保護団体や里親募集サイトから譲渡を受ける
・譲渡会で直接出会う
ただし、誰でも簡単に迎えられるわけではなく、終生飼養の約束・飼育環境の確認・費用負担などの条件があります。
それでも、こうした場から新しい家族を迎えることで、救われる命が確かに存在します。
私たち NPO法人VariousColors でも、殺処分寸前だった犬や猫を保護し、新しい家族につなげる活動を続けています。
特に「噛みつきなどの問題で引き取り手がつかない犬」にもトレーニングを行い、人と安心して暮らせるようにサポートしています。
「引き取るのは難しいけれど応援したい」と思ってくださった方は、寄付という形で命を守る活動を支えていただけます。
この記事ではさらに、殺処分の現状や犬猫を迎える前に知っておくべきことを詳しく解説します。
どうか最後までお読みいただき、あなたなりの一歩を考えてみてください。
その前に少しだけ自己紹介します
NPO法人ヴァリアスカラーズの代表理事を務めさせていただいております渥美直幸と申します。
私は20代前半に犬の訓練を学び、その後ペット専門学校の講師を続けながら、犬の訓練士として家庭犬の問題行動の改善やお悩み相談などを行ってきました。これまで多くのスタッフや飼主様に支えられ、そして何より多くの犬や猫に助けられ今があります。その感謝の思いから、42歳の時にヴァリアスカラーズを立ち上げました。小さいながらも保護施設を建設し、今に至ります。
まだまだ未熟な私ではありますが、私の残りの人生で出来ることは何か?と考え、将来もっと犬や猫を取り巻く環境がクリーンな世界として残せるように、一歩一歩前進したいと思い日々活動させていただいております。
目次
1. はじめに
- 日本の動物殺処分の現状
- 殺処分を減らすためにできること
2. 犬や猫を引き取る方法
- 動物愛護センターからの譲渡
- 保護団体やシェルターからの譲渡
- 里親募集サイトの活用
- ヴァリアスカラーズでは
3. 引き取る際に考えるべきこと
- 迎える前に確認すべきポイント
- 飼育環境の準備
- 経済的負担と時間の確保
4. 迎えた後のケアと注意点
- 健康管理と医療ケア(ワクチン・避妊去勢手術など)
- 新しい環境への慣らし方
- しつけと生活習慣の整え方
5. 引き取る以外にできること
- 一時預かりボランティアになる
- 保護団体への寄付や支援活動
- 殺処分ゼロを目指すためにできること
6. まとめ
- 大切な命を救うためにできる一歩
- 「引き取る」ことの意義と責任
1. はじめに
日本の動物殺処分の現状
日本では、毎年多くの犬や猫が保護施設に収容され、その中には新しい飼い主が見つからずに殺処分されてしまう動物もいます。環境省のデータによると、近年は譲渡活動の活発化や意識向上により殺処分数は減少傾向にありますが、それでもゼロにはなっていません。
なぜ殺処分が行われるのか?
飼い主による飼育放棄(「引っ越し先で飼えない」「高齢になり世話ができない」「飼い主様が先にお亡くなりになる」など)
野良犬・野良猫の増加(避妊・去勢されずに繁殖し続ける)
多頭飼育崩壊(適切に管理できず、飼い主・繁殖者などが手放すケース)
動物愛護センターや保健所は、収容した動物たちの新しい飼い主を探す努力をしています。しかし、すべての犬や猫が引き取られるわけではなく、一定期間を過ぎると殺処分の対象となることもあります。
殺処分を減らすためにできること
殺処分を減らすためには、一人ひとりの行動が重要です。
1. 引き取るという選択肢
ペットショップではなく、保護犬・保護猫を家族として迎えることが、救える命につながります。
2. 避妊・去勢の推進
不幸な命を増やさないために、適切な繁殖管理が必要です。
3. 終生飼育の意識を持つ
「飼えなくなったから手放す」のではなく、生涯を共にする覚悟を持つことが大切です。
4. 支援や啓発活動に参加する
直接引き取ることが難しくても、保護団体への寄付やボランティア活動、SNSでの情報拡散など、できることはたくさんあります。

2. 犬や猫を引き取る方法
「殺処分される犬や猫を引き取りたい」と思ったとき、具体的にどうすればよいのでしょうか?保護された動物たちは、いくつかの方法で新しい飼い主を探しています。ここでは、動物愛護センター・保護団体・里親募集サイトの3つのルートを分かりやすく紹介します。
① 動物愛護センターからの譲渡
動物愛護センター(自治体の施設)では、迷子になった犬や猫、飼い主に持ち込まれた動物などを保護しています。とはいえ、余談ですが飼い主様が分かっている犬や猫を素直に受け取る行為はしないと思いますが・・・。新しい家族を募集する「譲渡会」を開催していることもあるでしょう。
【手続きの流れ】
1. ホームページで情報を確認
各自治体の愛護センターには、譲渡対象の犬や猫の情報が掲載されています。
2. 譲渡会に申し込む
施設によっては、事前講習を受ける必要がある場合もあるようです。
3. 動物と対面し、適性を確認
性格や健康状態を確認し、家族として迎えられるか考えます。
4. 必要な書類を提出し、譲渡手続き完了
施設によってはトライアル期間を設けていることもありますので利用することをお勧めします。
●メリット: 費用が安く、行政機関が運営しているため信頼性が高いとされますが、そこで担当しているものが必ずしもその分野に精通しているとは限らないため、正しくは犬や猫に詳しい人を先に見つけておくとよいでしょう。
●デメリット: 上記にも記しましたが、行政機関で務めるもの=動物の行動などにおいて知識が薄いことがあることを知っておくとよいでしょう。
★ポイント
動物愛護センターの譲渡条件(終生飼育・避妊去勢手術の実施など)がありますのでそれを確認しておきましょう。
施設によっては、事前講習や審査が必要な場合があるのが当たり前ですので、先に確認しておくとよいでしょう。
② 保護団体やシェルターからの譲渡
民間の保護団体やシェルターも、殺処分対象になった犬や猫を保護し、新しい飼い主を探しています。団体によっては、ペットが一度家庭環境を経験している「一時預かり制度」を活用しているため、性格やしつけの情報が詳しく分かることもあります。
【手続きの流れ】
1. 保護団体のホームページやSNSで情報を確認
2. 譲渡会や面会予約を申し込む
3. 保護団体の審査(家庭訪問・アンケートなど)
4. トライアル期間(お試し飼育)
5. 正式譲渡の契約を結び、家族として迎える
● メリット: 性格や健康状態が詳しく分かる担当者がしっかりと存在する。トライアル制度があることが多いので利用しましょう。
● デメリット: 譲渡条件が厳しく、譲渡までに時間がかかる場合がある。※私の知る限りあまりに度が過ぎることもあるので注意しておきましょう。中には子供がいるならダメだ!とされるケースすらあります。
★ポイント
保護団体の譲渡条件(里親希望者の年齢制限・飼育環境など)をしっかり確認しよう。保護団体=正しい行動正しい知識だ!と安易には考えないように不安は先に解決しておくようにしましょう。また譲渡会では、動物の性格や相性をしっかりチェックしましょう。
③ 里親募集サイトの活用
最近では、インターネットの里親募集サイトを通じて、犬や猫の新しい家族を探すケースも増えています。個人が直接譲渡を行う場合もあり、保護団体を通さずに引き取ることができることが特徴です。
【代表的な里親募集サイト?※個人的に検索したものです】
ペットのおうち(全国の里親募集情報を掲載)
ジモティー(地域ごとの里親募集)
OMUSUBI(保護団体が管理する里親募集サイト)
【手続きの流れ】
1. サイトで譲渡対象の動物を探す
2. 掲載者(飼い主・団体)に連絡を取る
3. 譲渡条件を確認し、直接面会する
4. 正式な譲渡契約を交わす
●メリット: 条件に合った動物を全国から探せる。
● デメリット: 個人間の譲渡はトラブルになるリスクがある。
★ポイント
里親詐欺(転売目的など)を防ぐため、信頼できる相手かしっかり確認しよう。
事前に契約書を交わすことで、トラブルを防ぐことができる。
これはあくまでも個人の意見ですが、間に入る団体※募集サイトがどこまでその犬や猫の行動に責任を果たすのか?が大きな問題のような気もします。掲載されている犬猫が本当に記載されているような性格で行動を示しているか?は次の里親様のためにも大切にしないといけないものではないか?と考えてしまいます。

④ヴァリアスカラーズでは
私たちヴァリアスカラーズでも、保護した犬や猫を新しい家族につなげる譲渡活動を行っています。
「里親になりたい」と思っていただく方が安心して迎えられるよう、譲渡にはいくつかのステップを設けています。
まず、里親希望の方には譲渡条件を確認させていただきます。終生飼養できる環境があるか、住宅や家族構成は適しているかなど、動物と人が安全に暮らせるための基本条件です。
次に、希望する動物との面会・マッチングを行います。犬や猫の性格、年齢、体格、健康状態、問題行動の有無などを考慮し、生活環境に合った子を選んでいただきます。いきなり引き取るのではなく、まず触れ合いを通じて「この子と一緒に暮らせるか」を確かめていただけます。
さらにトライアル期間を設けています。通常は14日以上、最大1か月間、自宅で実際に生活していただきます。この期間に想定外の問題がないかを確認し、双方が安心して譲渡できるようにしています。
特にヴァリアスカラーズでは、「噛みつき」などの理由で処分寸前だった犬にも専門的なトレーニングを行い、人と安全に暮らせる状態にしてから譲渡します。そのため、里親さんにとっても「問題行動のある犬をいきなり迎える」心配は少なく、私たちがしっかりサポートします。
里親になるにあたっては、賛助会員として初年度8,000円をご協力いただく場合があります。これは、動物たちの医療費や生活費の一部として、責任を持って飼育いただくためのものです。もちろんその後の食費や医療費などは里親さんの負担となりますが、私たちも飼育やしつけの相談を随時受け付けています。
「高齢だけど里親になれる?」「初めて犬や猫を飼うけど大丈夫?」といった不安がある方もご安心ください。動物の性格や状況次第で、条件を柔軟に調整しながら対応しています。まずはお気軽にご相談いただけます。
詳しい譲渡の流れや条件については、こちらのページでご案内しています。引き取りを具体的に検討されている方は、ぜひ一度ご覧ください。
👉 ヴァリアスカラーズでの譲渡までの流れはこちら
3. 引き取る際に考えるべきこと
保護犬・保護猫を迎えることは、尊い命を救う素晴らしい行動です。しかし、安易に「かわいいから」「助けたいから」という理由だけで引き取るのは危険です。この判断をしてしまえば元の木阿弥、ペットショップなどから安易に購入した結果が一定数の飼育放棄となっているから今の現実がるのです。新しい家族を迎える前に、しっかりと準備し、責任を持って飼育できるかを考えましょう。ここでは、引き取る前に確認すべきポイント・飼育環境の準備・経済的負担と時間の確保について、分かりやすく解説します。
① 迎える前に確認すべきポイント
犬や猫を引き取る前に、まず「本当に最後まで責任を持てるか?」をしっかり考えましょう。
▢ 家族全員が賛成しているか?
→ 家族の中に動物アレルギーがある人はいませんか?生活スタイルに合っていますか?
▢ 終生飼育(最期まで世話をする覚悟)があるか?
→ 犬や猫は10年以上生きることが多いです。引っ越しやライフスタイルの変化に対応できますか?
▢賃貸や集合住宅の場合、ペット可かどうか確認したか?
→ 事前に契約書を確認し、ペットの飼育が許可されているかを確かめましょう。
▢ 旅行や出張時の預け先を確保できるか?
→ 長期間家を空ける場合、ペットホテルや信頼できる預け先を考えていますか?そこには必ず費用もかかります。
▢ しつけや病気になったときの対応ができるか?
→ しつけや健康管理には時間と労力がかかります。問題行動が出たときに、根気よく向き合えますか?
② 飼育環境の準備
新しい環境に馴染みやすくするために、迎え入れる前に準備しておくべきものをチェックしましょう。
▢トイレ・トイレシート(猫ならトイレ砂)
▢ 食器・フード(年齢や体質に合ったもの)
▢ ベッド・クッション(安心して休めるスペースを作る)
▢ ケージやキャリーケース(移動時やしつけ用)
▢ 首輪・リード(犬猫必要に応じて)
▢ おもちゃ・爪とぎ(ストレス発散用)
また、家の中の安全対策も必要です。誤飲しやすいもの(小さなものやコード類)は片付け、脱走防止のための対策も行いましょう。
③ 経済的負担と時間の確保
犬や猫を飼うには、毎月の費用と緊急時の医療費が必要になります。
おおよそかかる費用の目安
| 費用項目 | 犬 およそ年間費用 | 猫 およそ年間費用 |
| フード代金など | 4万~11万 | 3万~7万 |
| トイレ用品など | 2万~4万 | 2万~3万 |
| ワクチン・予防接種など | 1万~2万 | 1万~2万 |
| 健康診断・医療費など | 2万~6万 | 1万~5万 |
| しつけ・トレーニング | 3万~6万 | |
| その他おもちゃ、シャンプーなど | 2万~ | 2万~ |
| 合計 | およそ14万~ | およそ9万~ |
また、突発的な病気や怪我のために、ペット保険に加入するか、緊急時の医療費を貯金しておくことも大切です。
必要な時間の目安 ※連続して取らずとも、一日のトータルで考えればそのくらいの接点は必要。
▢散歩(犬の場合):毎日30分~1時間(小型犬)、1時間以上(大型犬)
▢ 遊び・コミュニケーション:1日30分以上(ストレス軽減や健康維持のため)
▢ お世話(ごはん・トイレ掃除・ケア):1日1時間程度
「忙しいから十分にお世話できない」「経済的に余裕がない」と感じる場合は、一時預かりボランティアや保護団体からの支援など、他の方法で動物を助けることも検討してみてください。そもそもこの状況で飼育すべきではありませんが・・・
保護犬・保護猫を迎える前に、「本当に飼育できるのか?環境や経済面の準備は整っているのか?」をしっかり考えることが大切です。
「助けたい」という気持ちだけで迎えてしまうと、飼い続けられずに手放すことになり、結果的に動物を不幸にしてしまうこともあります。最後まで責任を持ち、大切な家族として迎えられる準備を整えましょう。


4. 迎えた後のケアと注意点
保護犬・保護猫を迎え入れたら、そこからが本当のスタートです。新しい環境に慣れさせるための工夫や、健康管理、しつけのポイントを知っておくことで、スムーズに共生できます。ここでは、健康管理・環境への慣らし方・しつけと生活習慣の整え方について、分かりやすく解説します。
① 健康管理と医療ケア
保護された犬や猫は、これまで十分な医療を受けきれない可能性ももちろんあります。引き取った後は、健康チェックと予防医療をしっかり行いましょう。
迎えたらすぐに動物病院へ!
健康診断(血液検査・便検査など)を受ける
ワクチン接種(狂犬病・混合ワクチン)を確認する
避妊・去勢手術の有無を確認し、必要なら手術を検討する
フィラリア・ノミダニの予防を始める
◎ 犬の場合
狂犬病ワクチンは法律で接種が義務付けられています。(年1回)
フィラリア症(蚊が媒介する寄生虫)予防を春~秋に行う必要があります。
◎ 猫の場合
室内飼いでも、ノミ・ダニ予防は必要です。
白血病ウイルス(FeLV)や猫エイズ(FIV)の検査も重要です。※多頭飼育される場合は先住猫含め注意が必要です。
健康管理のポイント
定期的な健康診断(年1回以上)で、病気の早期発見を。適切な食事管理で、年齢や体質に合ったフードを選ぶ。
② 新しい環境への慣らし方
保護された犬や猫は、人の生活や人そのものに慣れていないことが多いです。そのため警戒心が強い場合があります。焦らず、ゆっくりと新しい環境に慣れさせましょう。
環境に慣らすためのステップ
1日目: まずは静かな環境で過ごし、人が無理に触らないようにする。
2~3日目: ごはんやトイレの場所を覚えてもらうことを中心にそれ以外人からの接触を強く懇願しないこと。
1週間~: 少しずつスキンシップを増やし、散歩や遊びの時間を作る。
ポイント
犬・猫ともに「隠れられる安心できるスペース」を用意することが大切。※ここにケージを利用することが何より大きなポイント
大きな音や急な動きは怖がるので、できるだけ静かに接する。
しつけを急がず、「この家、もしくはこのケージ内は安全な場所」と感じさせることが最優先。
犬の場合
散歩は慎重に!突然、人の生活の一部分を経験させようと頑張りすぎると急な行動に出ることもあるでしょう。まずは室内やお庭などでお散歩の模擬練習を何度も行い関係を作るべきでしょう。このタイミングで飼い主様はしつけを学ぶべきです。
人に慣れていない犬は、焦らずゆっくり信頼関係を築く。
猫の場合
新しい家では最初、狭い一部屋※ケージからスタートさせると安心しやすくその後の人との距離感も縮めやすい。
いきなり抱っこや接触を考えることは猫に逃げるを植え付けることもあるため、猫のペースに合わせて慣らしていく。
③ しつけと生活習慣の整え方
保護犬・保護猫の中には、過去の経験から問題行動を持っている子もいます。「噛む・吠える・粗相する」などの行動には、適切な対処が必要です。
犬のしつけのコツ
叱るのではなく、ほめるしつけを意識する!など考えやすいが専門家※犬のトレーナーと関係を作ってい置いた方が無難です。
トイレの失敗は怒らず、成功したときにしっかり褒める
様々な問題が起こりうることもあるため、必ず自己判断または保護施設や行政の考えを鵜呑みにせず犬のトレーナーさんに相談する癖をつけておきましょう。
猫のしつけのコツ
爪とぎの場所を決めて、家具を傷つけないようにする。
トイレの失敗が続く場合は、トイレの場所や種類を見直す。そもそも最初から飼育空間を大きく与えない、しっかり人に甘える姿が見えてくるのと同時にゆっくり行動範囲を大きくしていきましょう。
④ 長く幸せに暮らすために
犬や猫を迎えたら、「可愛いから」「助けたいから」だけではなく、生涯をともにする覚悟を持つことが大切です。
飼い主ができること
シニア期(高齢)になったときの介護を考えておく※時間と労力がかかるものとして覚悟しておく。
病気やケガのときに対応できるよう、ペット保険や医療費の準備をする
災害時の避難方法を考えておく(同行避難の準備)飼い主様と移動することが出来なければ助けることも出来ない事実を今のうちに理解キャリーなどに犬猫をスムーズに入れることが出来るようにすることが義務である。
ペットと避難するための備え
キャリーケース・リード・フード・水を常備しておく。
避難所にペットが受け入れられるかを事前に確認。
災害時には、迷子にならないようマイクロチップや名札をつける。
まとめ
保護犬・保護猫を迎えた後は、健康管理・環境への慣らし・しつけの3つが大切です。
✔ 迎えたらすぐに動物病院で健康チェックを受ける
✔ 新しい環境に慣れるまで時間をかけてゆっくり接する
✔ しつけは「叱る」よりも「ほめる」ことを意識する※失敗したくなければ独学より専門家を。
✔ 長く幸せに暮らせるよう、シニア期や災害時の備えも考える
大切な命を迎えるということは、最期まで責任を持つこと。
「この家に来てよかった」と思ってもらえるよう、愛情を持って寄り添いましょう。

5. 引き取る以外にできること
「犬や猫を助けたい」と思っても、さまざまな理由で引き取ることが難しい場合もあります。
しかし、引き取る以外にも動物たちを救う方法はたくさんあります。
ここでは、一時預かりボランティア・保護団体への寄付や支援・情報発信の重要性について、分かりやすく解説します。
① 一時預かりボランティアになる
「飼い続けるのは難しいけれど、短期間なら世話ができる」という方には、一時預かり(フォスターペアレント)という方法があります。
一時預かりとは?
保護団体が保護した犬や猫を、新しい飼い主が見つかるまで一時的に預かる活動。
シェルターの負担を軽減し、より多くの命を救うことができる。
実際に動物をお世話することで、「自分に飼えるかどうか」を判断する機会にもなる。
【一時預かりの流れ】
1. 保護団体の募集情報を確認し、申し込む。
2. 面談や自宅環境のチェックを受ける。
3. 指定期間(数週間~数カ月)、動物を預かる。
4. 里親が決まるまで、世話をしながら成長を見守る。
ポイント
一時預かりでも、飼育環境のチェックや審査がある。
里親が決まるまでの期間はケースバイケース。
② 保護団体への寄付や支援活動
直接引き取ることができなくても、金銭的な支援や物資の寄付で保護活動をサポートできます。
保護団体への支援方法
寄付をする(毎月の支援・単発の寄付)
フードやペット用品を送る(保護団体が必要としているものを事前に確認)
ボランティア活動に参加する(譲渡会の運営・シェルターの清掃など)
寄付が役立つ理由
保護団体は、医療費や施設維持費など多くの資金を必要としている。
犬や猫の食事・ワクチン・避妊去勢手術の費用をまかなうことができる。
どんな物資が喜ばれる?
ペットフード(賞味期限が長いもの)
トイレシート・猫砂
ブランケットやタオル(寒さ対策)
ケージ・キャリーケース(移動用)
物資を送る前に、必ず保護団体の公式サイトで「必要なもの」を確認!
③ 殺処分ゼロを目指すための情報発信
「保護犬・保護猫の存在を知ってもらうこと」も、殺処分を減らすための大切なアクションです。
情報発信でできること
SNSで里親募集の投稿をシェアする
保護犬・保護猫の現状を広める記事を読んで共有する
家族や友人に「ペットを迎えるなら保護犬・保護猫も選択肢」と伝える
情報発信がなぜ重要?
「知らなかった」人に届けることで、新たな里親が見つかる可能性が広がる。
「ペットショップで買うのが当たり前」という考えを変えるきっかけになる。
犬や猫を引き取ることが難しくても、一時預かり・寄付・情報発信など、支援できる方法はたくさんあります。
短期間のお世話ができるなら、一時預かりボランティアに挑戦!
金銭的な支援や物資の寄付で、保護活動をサポート!
SNSや口コミで情報を広めることも、大切なアクション!
「自分にできることは何か?」を考え、少しでも多くの命を救うために行動してみましょう。
当団体ヴァリアスカラーズへのお問い合わせ・寄付情報はこちら

■特定非営利活動法人VariousColors こちらをクリック ⇒ [公式サイト]
■保護犬猫紹介ページ こちらをクリック ⇒ [犬猫里親募集]
■ご支援・ご協力ページ こちらをクリック ⇒ [ご支援ページ]
■団体インスタグラム こちらをクリック ⇒ [インスタグラム]
6. まとめ
ここまで、殺処分される犬や猫を引き取る方法や、迎える際の準備・ケア・支援の方法について解説してきました。最後に、保護犬・保護猫を迎える意義と、私たちにできることを振り返りましょう。
① 大切な命を救うためにできること
日本では、毎年多くの犬や猫が飼い主を失い、行き場をなくしています。
その中には、新しい家族が見つからず、殺処分されてしまう子たちもいます。
しかし、私たち一人ひとりの行動で救える命があります。
保護犬・保護猫を迎えることの意味
「ペットを迎えるなら、保護犬・保護猫も選択肢に」
「ペットを飼うことは、最後まで責任を持つこと」
「一人ひとりの行動が、殺処分ゼロに近づく一歩になる」
ペットショップでの購入ではなく、保護された犬や猫を迎えることで、1つの命が救われる。
その小さな選択が、「殺処分ゼロ」につながる大きな力になります。
② 引き取る前にもう一度確認しよう
「保護犬・保護猫を迎えたい」と思ったら、本当に最後まで世話ができるか?をしっかり考えましょう。
飼う前にチェックすること
終生飼育の覚悟があるか?(寿命は10年以上)
家族全員の同意を得ているか?(ペット可の住宅かどうかも確認)
経済的に余裕があるか?(年間の飼育費用を把握する)
病気や高齢になったときも世話ができるか?
旅行や仕事で家を空けるときの対応を考えているか?
「かわいいから」「助けたいから」だけで迎えるのではなく、犬や猫の一生に責任を持てるかを考えることが大切です。
③ できることは「引き取る」だけじゃない
もし「今は引き取ることができない」と感じても、ほかにもできることはたくさんあります。
一時預かりボランティアとして支援する(短期間だけ世話をする)
保護団体に寄付する(医療費や飼育費をサポート)
SNSで情報発信する(保護犬・保護猫の存在を広める)
「今すぐ迎えられなくても、できることがある」という意識を持つことが、動物たちを救う第一歩です。
④ 最後に:あなたの行動が未来を変える
保護犬・保護猫を迎えることは、1つの命を救う大きな決断です。
そして、それだけでなく、「ペットを飼うとはどういうことか?」を考えるきっかけにもなります。
もしあなたがこのコラムを読んで、「動物たちのために何かしたい」と思ったら
小さなことでも、できることから始めてみてください。
あなたの行動が、救われる命を増やし、殺処分ゼロの未来へとつながります。
「ペットを迎えるなら、保護犬・保護猫を。」
その選択が、幸せな未来をつくる第一歩です。
当団体ヴァリアスカラーズへのお問い合わせ・寄付情報はこちら
■特定非営利活動法人VariousColors こちらをクリック ⇒ [公式サイト]
■保護犬猫紹介ページ こちらをクリック ⇒ [犬猫里親募集]
■ご支援・ご協力ページ こちらをクリック ⇒ [ご支援ページ]
■団体インスタグラム こちらをクリック ⇒ [インスタグラム]